スティーブン・R.コヴィー氏の著書である「7つの習慣」には、同じ内容でも
- 翻訳の新旧
- 特装版、完訳版、普及版、○周年の記念版
など、いくか種類があります。
もしこれから買うのであれば、完訳の30周年記念版がオススメです。(下記で紹介しますが、完訳版と普及版は本のサイズが違うだけ)
今回は、各出版社や本ごとの違いについてまとめてみました。
活字本の比較
まずは普通の活字本。大きく分けて、絶版になっているものを含めると3種類あります。
人生を成功させる7つの秘訣(1990年)
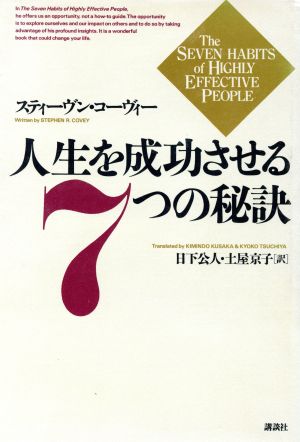
講談社から1990年9月に出版された、日本で最初の翻訳本。現在は絶版。
文章の表現は硬く、目次も見ただけで本嫌いな人は受け付けなさそうです。
- 前向きな姿勢 〜できるところから変えていく〜
- 自己変革への設計 〜最終目標を念頭においていきる〜
- 確実な自己管理 〜スケジュール管理は自己管理〜
- 相互依存のために 〜自分も勝つ、相手も勝つ〜
- 相互理解の地平線 〜まず、わかろうとする〜
- シナジーを発揮する 〜違いをバネに飛躍する〜
- 毎日刃を研ぐ 〜バランスのとれた自己再生のために〜
「中古取引されていることも多い」と書かれているサイトもあったのですが、ぼくの住んでいる地域にある大きな古本屋では見つけることができませんでした。
どうしても読みたいなら、東京にある国立図書館で閲覧するのがいいかもしれませんね。国内で発刊された本なら全てそろっているので。
7つの習慣(1996年)
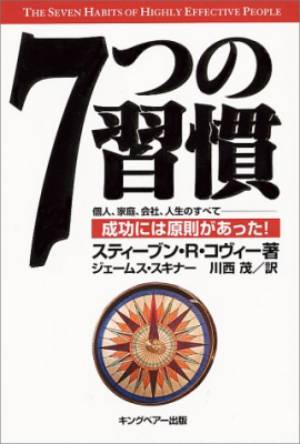
正式名称は「7つの習慣 成功には原則があった!個人、家庭、会社、人生のすべて」。キングベアー社から1996年12月に出版されました。
文章そのものは、1つ目のものよりは難しくなく、高校の国語の教科書レベルです。
発売された当時は「現代の自己啓発の原点」と称され、バブル崩壊後の情勢もあったことから、自分と社会を見つめ直すきっかけになった!と言われていたそう。
なので、最初に発刊されたものとの大きな違いとすれば、成功へ導くための原則にちなんだ内容となっている点でしょうか。
後に紹介する「完訳版」と比較すると、出版社が『成功には原則があった!』と副タイトルをつけたくなるのも分かる気がします。
- 主体性を発揮する
- 目的を持って始める
- 重要事項を優先する
- Win-Winを考える
- 理解してから理解される
- 相乗効果を発揮する
- 刃を研ぐ
昭和の時代に生まれてないので想像にはなっちゃうんですが、当時は「ビジネス書はビジネスマンが読むべき」という考え方が強かったのかもしれません。
ちなみに、2005年〜2011年にかけて、同出版社から講演などを収録したCD・DVD付きの限定版が発売されています。
いまはYouTubeで解説している人も多いし、そもそもプレミア価格がついており手が届かないので、あえて買う必要はないと思いますけどね。
完訳 7つの習慣(2013年)
コヴィー氏の没後1年をきっかけに、キングベアー社から2013年8月に出版されたハードカバー本。
より原著にそった内容となっており、日本語もさらに分かりやすくなっているため、今から読むなら完訳版がオススメです。
個人的には、ビジネスマンなどの超具体的な人に向けたものではなく、誰にでも受け入れられそうな抽象的な表現となっているように感じました。
- 主体的である
- 終わりを思い描くことから始める
- 最優先事項を優先する
- Win-Winを考える(変更なし)
- まず理解に徹し、そして理解される
- シナジーを創り出す
- 刃を研ぐ(変更なし)
生き方が多様化している現代だからこそ、壁を作らず読んでほしいという気持ちが込められているんでしょうね。
普及版(2020年)
2013年に出された完訳版を、2020年1月に新書サイズで出版したものが「普及版」。内容はハードカバー本と全く一緒です。
家でゆっくり読むならハードカバー本でいいかもしれませんが、出張中にカバンで持ち運んだりするなら、新書サイズにしたほうが便利だと思います。
また、完訳版なら電子書籍もあります。ぼくは紙で読みたい派なので、あまり使ったことはないですが……
紙で読みたいけどゴテっとしたハードカバー本はちょっと、という人向けのものなんでしょうね。
30周年記念版(2020年)
さらに、2020年10月には「30周年記念版」という新しいカバー本が発売されました。
内容は完訳版とほぼ一緒。「コヴィー氏の息子・ショーン氏による、約130ページの加筆がある」だけですが、値段は2013年に発刊された完訳版と同じです。
これから買うのであれば、加筆があるぶん記念版のほうが良いでしょう。
マンガ本の比較
次はマンガ化された本の比較。といっても、2種類しかありません。
まんがと図解でわかる7つの習慣(2011年)
上記の「旧・7つの習慣」のヒットを受け、スティーブン・R. コヴィー氏が直々に監修した図説版。大型版が2011年9月に、文庫版が2013年に出版されています。
図柄を使ってイメージしやすくしたかったんでしょうけど、肝心の解説文が難解であり、マンガ化する意味があまりなかったように感じました。
(後に出版された、新マンガ版のほうが格段に読みやすいです)
生前のコヴィー氏の単独インタビューが載せられている点では、レアな本だと思います。
マンガでわかる 7つの習慣(2013年〜2015年)
完訳版がベストセラーとなったことを受け、宝島社がマンガ版としてシリーズ化したもの。全4巻。
初代である2011年版とは違って、本の9割をマンガで占めているので、活字を読むのが苦手でもとっつきやすいです。
また最終巻では、7つの習慣の続編である『第8の習慣「効果」から「偉大」へ』にも触れられています。ぶっちゃけ通して見るなら活字本よりマンガ版のほうが読みやすいかも……とすら感じました。
完訳で挫折しそうなら、さっさとマンガ版に切り替えたほうが賢明かもしれません。
マンガ版にありがちな「なんか原作と解釈が違くない?」といったこともなく、言っている要素は一緒なので、そこは安心して大丈夫です。
ちなみに、2016年には「まんがでわかる7つの習慣 Plus」という続編?にあたる本が出ていますが、1〜4巻まで読んだ人なら必要ないかなぁと思います。
逆に、これまで7つの習慣を読んだことがなく、4巻ぜんぶ揃えるのもなぁ……という人にとってはいいかもしれませんね。
まとめ
「7つの習慣」の出版社や翻訳の違いについてまとめてみました。
他にも「7つの習慣」をもじったものや、二次創作のような本は見受けられますが、しっかり原作を受け継いでいるのは上記だけだと思います。
ひとつの参考として、チェックしてみてください!
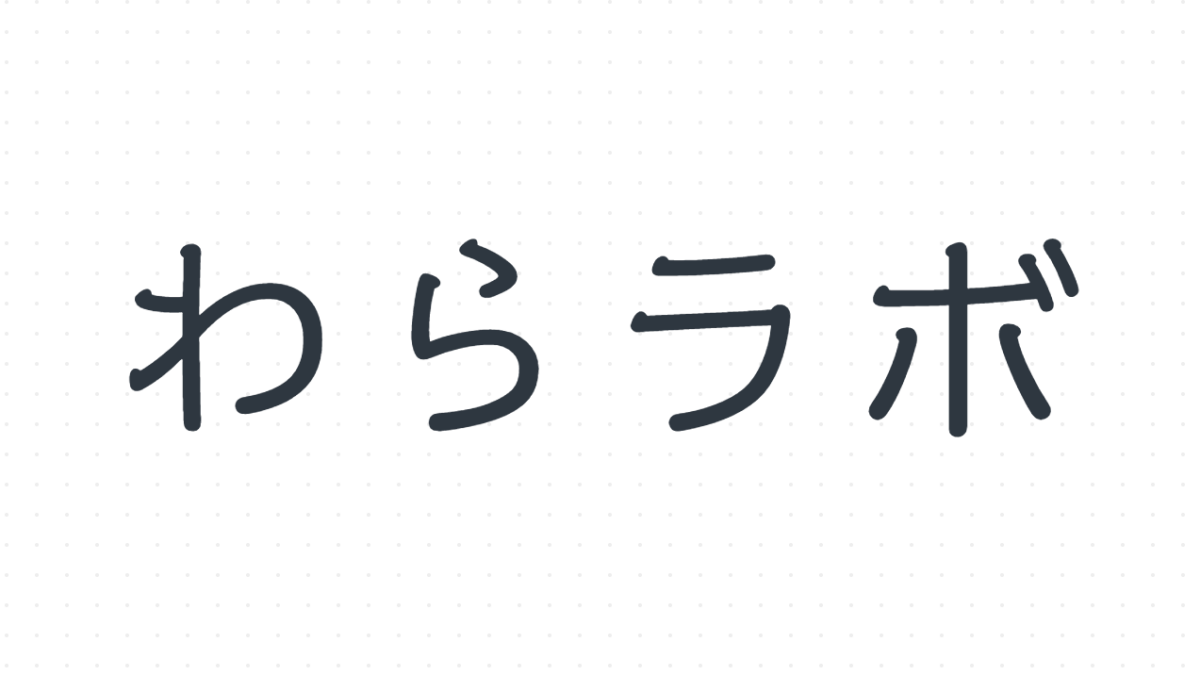

![完訳7つの習慣 30周年記念版 [ スティーブ・R.コヴィー ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1014/9784863941014.jpg?_ex=128x128)
![完訳7つの習慣 人格主義の回復 [ スティーヴン・R.コヴィー ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0246/9784863940246.jpg?_ex=128x128)
![完訳7つの習慣普及版 人格主義の回復 [ スティーブン・R・コヴィー ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0925/9784863940925.jpg?_ex=128x128)
![まんがと図解でわかる7つの習慣 (宝島sugoi文庫) [ スティーヴン・R.コヴィー ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5780/9784800205780.jpg?_ex=128x128)
![まんがでわかる7つの習慣 [ 小山鹿梨子 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5314/9784800215314.jpg?_ex=128x128)
![まんがでわかる7つの習慣Plus [ 小山鹿梨子 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9128/9784800249128.jpg?_ex=128x128)